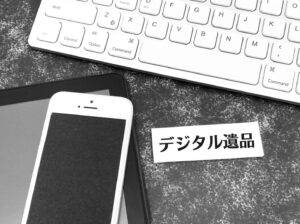(JR衣笠駅からバス乗車 バス停「衣笠城址」下車徒歩10分)
平安時代の“前九年合戦”で源頼義に従い活躍した“平為通”は頼義から三浦の地を賜り“三浦氏”を名乗り半島の中心部に衣笠城を築きます。
為通は三浦氏の初代です。2代為継、3代義継は“後三年合戦”で源義家に従い活躍します。
横須賀市の清雲寺(せいうんじ)は、義継が父為継の菩提を弔うために創建しています。
三浦一族は桓武平氏の出自ですが、清和源氏との結びつきが深いのです。
“本尊滝見観音像”は国重文です
◆同像は中国南宋時代の製作と考えられています
同寺本尊の滝見観音菩薩像は、もと同市大矢部二丁目にあった円通寺の本尊でしたが廃寺となり同寺に移坐されました。
像は右ひざを立て左ひざを垂下させた、くつろいだ姿勢。
面長で鼻筋が細い顔立ちなど、妖艶さを漂わせる印象があり、着衣のしわ等は中国南宋時代の特色を示します。
中国文化の流入を伝える貴重な国重文の像です。

本堂背後には三浦氏3代の五輪塔が立ちます
◆元は円通寺やぐら群にあった石塔群も合わせて立ちます
本堂背後の墓地には三浦氏3代の五輪塔が立っています。
元々は2代為継の五輪塔だけでしたが、後に円通寺の裏山やぐら群にあった初代為通、3代義継の五輪塔も移し立っています。
「石造板碑」および「三浦九十三騎墓」(初代為通と共に三浦の地に移ってきた武士たち)と伝えられる石塔群も同時期に移されました。

“毘沙門天像”は矢請の毘沙門と呼ばれています
本堂内に安置の毘沙門天像は、元は同寺の本尊仏でした。寺伝では、和田合戦の折に、和田義盛を守るために敵の矢を止めたと言われ、“矢請(やうけ)の毘沙門天”と呼ばれています。像高70.7cmの寄木造、彩色玉眼入りです。邪鬼の上に立ち、腰をやや左に張ってひねり、右手に宝珠、左手に五輪塔を捧げる立像で県重文です。
かん治さん
「鎌倉検定は1級で お酒は2級を飲んでいまして、プレゼントをいただきますと喜んでサンキュウと言っています」がお決まりの自己紹介。
「鎌倉ガイド」としても活躍する湘南通のアマチュア落語家。