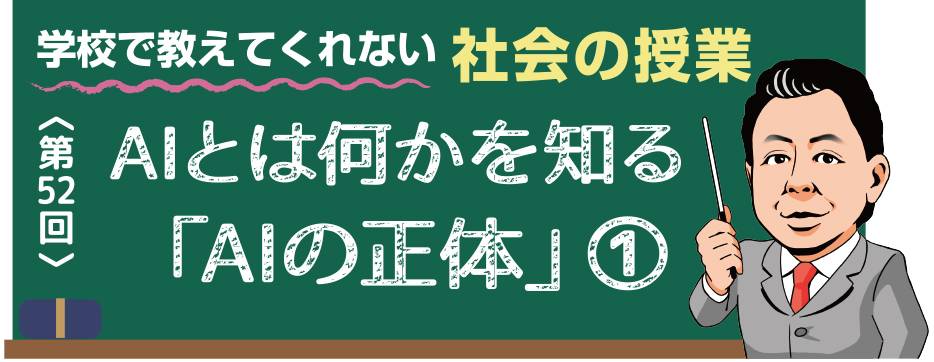
【2025年9月27日号 vol.52】
社会人大学 代表コンサルタントの桑名 伸です。
「学校で教えてくれない社会の授業」では、学校では教えてくれない社会の本質を学び、幸せになるための(不幸にならないための)正しい考え方についてお伝えします。
AIとは何かを知る
「AIの正体」①
ここ最近の授業では「AI」について取り上げていますが、「AIはすごい」「便利」「仕事が捗(はかど)る」等、肯定的な意見がある一方、「AIが人間の仕事を奪う」「AIに頼ると人間の能力が落ちる」というAIについて否定的な意見や不安の声があるのも事実です。
今回の授業ではAIとは何か…、「AIの正体」について考えていきます。
今回の授業でAIに振り回されるのではなく、AIを使いこなす側の人間になっていただければと思います。
前号で読者様からの質問に対するAIの回答と私「人間桑名」の回答を紹介しました。
結論からいうと、
①AIは計算・検索を素早くできる
②明確な答えが無いものには対応できない
大くくりでいうとこのような感じになります。
①については言うまでもなく、計算をすさまじい速度で行えます。
そしてその「計算」は数学的なものだけではなく、文字の組み合わせや意味の精査や要約などをインターネット上の莫大な情報を集めて計算して回答してくれます。AIは計算が得意です。
②は、①で計算とお伝えしましたが、その計算をするにはもとになる材料が必要です。
例えば、1+2=3というのは「1」と「2」という材料が分かっています。だから計算ができるのです。
皆さんがAIはすごいと思う原因の一つは、AIが計算するときにこの「1」や「2」が数字のように単純なものではなく複雑な材料を持ってきて計算するからです。
でも多数の情報やその組み合わせは複雑といえども「材料を持ってきて計算ができる」ものに過ぎないのです。
前回の授業のAIと私の回答の比較を見るとわかりやすいと思います。
(前回の授業はこちら >> 第51回)
ゆゆさんの前回の投稿に関してAIの言葉選びは秀逸ですが、当たり障りのない優しい言葉の投げかけに終わっています。
自画自賛のようで恐縮ですが、「人間桑名」の回答は、その答えが本当に正しい結果かどうかは別として、質問相手がどうやったらうまくいくかという「解決方法」を考えて答えています。
AIは多数の情報を集め「瞬時に計算する便利屋さん」と言えるでしょう。
その計算のための材料、つまり情報はインターネット情報、もしくはサーバー内に蓄積した情報の中に限られます。世界中のインターネット情報が膨大なだけにいろいろな角度の計算を瞬時に行ってくれるわけです。
これをみて「すごい」という意見が多数出てくるのは理解できます。
しかし「AIはすごい」を通り越して「万能」まで話をもっていく考えや動きは問題です。
AIをビジネスにしている側、AIの話題でアクセスカウントを集めたい人があおり、「AIの正体」を知らない人が騒いでいるのが現実なのです。
AIを恐れることなく、心配することなくうまく使いこなす側でいるためにも「AIの正体」を知りましょう。
今までの説明で少しその理解が進み始めたと思いますが、「AIの正体」を知るために一番大切なのは「AIの限界」を知ることです。
〈AIの限界を知れば怖くない〉
以前にもご投稿いただいた「おことさん」からです。タイムリーなのでご紹介します。
投稿ネーム:おこと 32歳 女性
相談内容:
とてもタイムリーに、この記事を読みました前日に、初めてCopilotを会社で使用したので、気付きと考えを投稿させていただきます。
まず、Copilotはものの数分もしくはそれ以下であらゆる資料をまとめて、その指示もとても短くて大丈夫で、これがいわゆるAIか…と感心しましたが、任せっぱなしではなくその後のチェックが大事というのは重々思い知りました。
また、教え込ませ方によって違う資料が出てくるのでやはり要点をつかんだ資料であれ、人間の気持ちを組み込んだものは出てきません。
ですが、数字を引っ張ってくる等のことは天才的だと感じました。
私の感想としては、Copilotに最初に読み込ませてパワーポイント等の成果物を出させると、その回答につられてそれ以降自分で考えることをやめてしまう、それが最も怖いです。職場の全員がCopilotに資料を放り込むことが仕事になりそうでした。
自分がやってきたことの軸や思いは自分しか知らないので、Copilotに作成させたとしてもメインのものは修正して、人間の気持ちが入った資料にしなければならないと思っています。とは言え、時短にもなるAIを活用して、組み合わせた効率の良い業務をみんなが身につける時代が来ると感激しました。
ありがとうございます。本当にタイムリーですね。
おことさんの文章からテキパキと仕事をこなすだけでなく、さらに人間としての味わい深い側面も兼ね備えている方とお見受けしました。
仕事をこなす「作業領域」と、人間としての味わい深い「わびさび」や相手への気遣いの効いた制作物やアウトプット。この両方が必要とおことさんは伝えてくれています。その両方をできる方だからこそAIについての悩ましい感覚を持つのでしょうね。
「AIの限界」を知れば「AIにやらせるべきこと」「AIにやらせてはいけないこと」「AIにはできないこと」がわかります。「AIにやらせてはいけないこと」は「AIの制作物の効果の限界」を知れば理解できます。
次回の授業ではここを掘り下げていきます。
社会人大学
代表コンサルタント
桑名 伸
「学校で教えてくれない社会の授業」では、皆さまの取り上げて欲しいテーマや、ご意見、ご感想をお待ちしております。
>>学校で教えてくれない社会の授業ご意見、ご感想投稿フォーム<<


