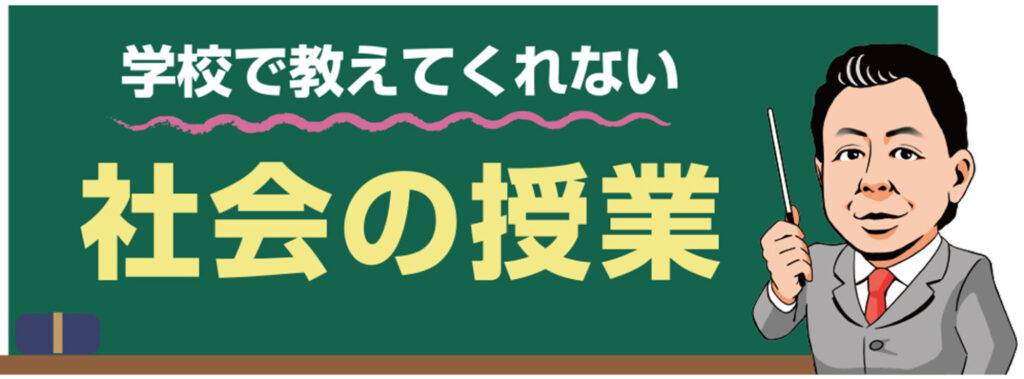
【2025年8月9日号 vol.50】
社会人大学 代表コンサルタントの桑名 伸です。
「学校で教えてくれない社会の授業」では、学校では教えてくれない社会の本質を学び、幸せになるための(不幸にならないための)正しい考え方についてお伝えします。
今回の授業では5月17日の授業で投げかけた
「考えない」癖について、癖になる理由とその大きなリスク
をお伝えします。
まずは5月17日の授業を今一度見てください。
5月17日の授業で「考えないことは大きなリスク」という内容で問題定義をしました。
今回はその答え、考えない癖がどうしてついてしまうのかとその結果の大きなリスクが何なのかを勉強していきます。
まずは「考えない癖がどうしてついてしまうのか」についてです。
●考えること自体が面倒に感じる。疲れる、辛い。
●考えようにも考える材料がわからない。
◆答えが明確になっているものにしか行動できない。
◆「すぐに結果が出るもの」にしか意識が向いていない。
他にもまだありますが、まずはこの部分を学んでいきましょう。
最初の2つの●と後の2つの◆に分けて勉強していきます。
●について
この●の2つは、「考える能力」の筋肉が足りていない状態です。考えること自体が面倒に感じる人は少なくないでしょう。
体を動かすのは好きだが頭を使うのは面倒という人も多いでしょう。体を動かすのも頭を使うのも面倒という猛者(?)もいるでしょう(笑)
また、2つの●は絡んでいることも多いです。
考えたくても、その「考える内容」が分からないのでそれを考えることが面倒になる、という感じです。若い方で「考えるのが苦手」という人に次のことを強くお伝えしたいと思います。
「考えることは最初はダルいかもしれないけど、慣れればなんてことない」
です。
以前から話している「筋トレ」と同じです。
これについては後ほど続きを話します。
〈考えない癖の原因〉
答えは簡単です。
「考えなくても何とかなってきたから」
です。
でも次のことを考えてみてください。
「このまま考えないでこの後の人生がうまく行くだろうか」
と。
その答えは、次のようにしてみると、簡単に見つけることができるでしょう。
・考えないで人生を成功させた人を探してみる
・成功している人が考えていたのかどうかを考えてみる
例えば野球の大谷選手、イチロー選手。タレントで映画監督の北野 武氏。彼らは考えて生きてうまくいっているのか、考えないでもうまくいっているのか。
注意してほしいのは、たまたま瞬間的にうまくいっただけの人を参考にしてはいけません。
「仮想通貨でもうけた」とか「〇〇で一発当てた」などなど。
あくまでも継続的に、中長期的にうまくいっている人を対象にすることが大切で「にわか成功」は対象から外してください。
なぜなら若い皆さんの成功させなければいけない人生は長いからです。
◆について
この◆の2つは、はっきりとした利益になる確証がないと動かないタイプです。エビデンス(証拠)主義と名付けます。
すぐに結果が出ないとそれは「うまくいかないこと」や「自分にはメリットがないこと」というカテゴリーにもっていってしまうタイプです。
最速で〇〇、秒で億を稼ぐ……、などなど。秒で億を…の方の例は、先ほどの人生レベルの成功の話の参考になると思います。(私は彼らは嫌いではありません。あくまでも例として)
あとは、システムやサービスで「簡単に〇〇できる」、「塗るだけで△△になる」みたいな商品の情報もあふれています。
この◆についての主な原因として、短期的な成功の情報があふれていてその情報をたくさん浴びていることと、中長期や人生レベルで成功している「本物」はSNSやネットでその考え方を伝えている人は少ないです。
「北野 武チャンネル」ってありますかね? 人生を深く考えて成功されている人はあまりネットで情報配信していない気がします。
また、成功のエビデンス(証拠)が無いと考えない、動かない、のリスクは明確です。
そういう証拠があれば誰もが考え動くので、結果的にそんなにうまくいかないことになります。
そもそも成功のエビデンスがあることはそれについて深く考える必要がなく、誰かが考えた結果を「自分がなぞれるかどうか」を考えるだけのことなので、ここでいう「考える」ということと次元が違います。
厳しい言い方だと「考えているフリ」、「考えるごっこ」に近いのです。
小さなことでいいのです。
自分の能力で、「これはできるのか」「そこに向かうべきか」「できるために能力は伸ばせるか」「何が必要か」…、このように深く自分のこととして考えることが人生の成功には必要なのです。
成功と言ってもビジネス上の話だけではなく、結婚や自分の仲間との関係や、どこのコミュニティーに属していくのかなど、考えることはたくさんあります。
間違いやすいのは自分の成功を他人と比較してそれに勝つことを考え続けることです。
一時的にはありでも、常に他人と比較をして優劣をつけることを目的としている人は後で辛くなります。自分自身のことを真剣に考えていきましょう。
最近は考えなくてよくなるサービスとしてAIがもてはやされています。
今回の授業でお伝えしたように、AIは「考えないでよい」を実現するツールなのかもしれません。
でもこのAI自体が良い・悪いと決めつけるのはそれこそ「考えない決めつけ」になります。
次回の授業では「考えないことのリスク」の続きと、その解決方法。
そして「AIの正しい利用と間違った利用」の授業を行います。
AIに支配される側の場合とAIをうまく利用する側の場合との話をします。
次回の授業の前に挿絵を置いておきます。
あなたはどっち?
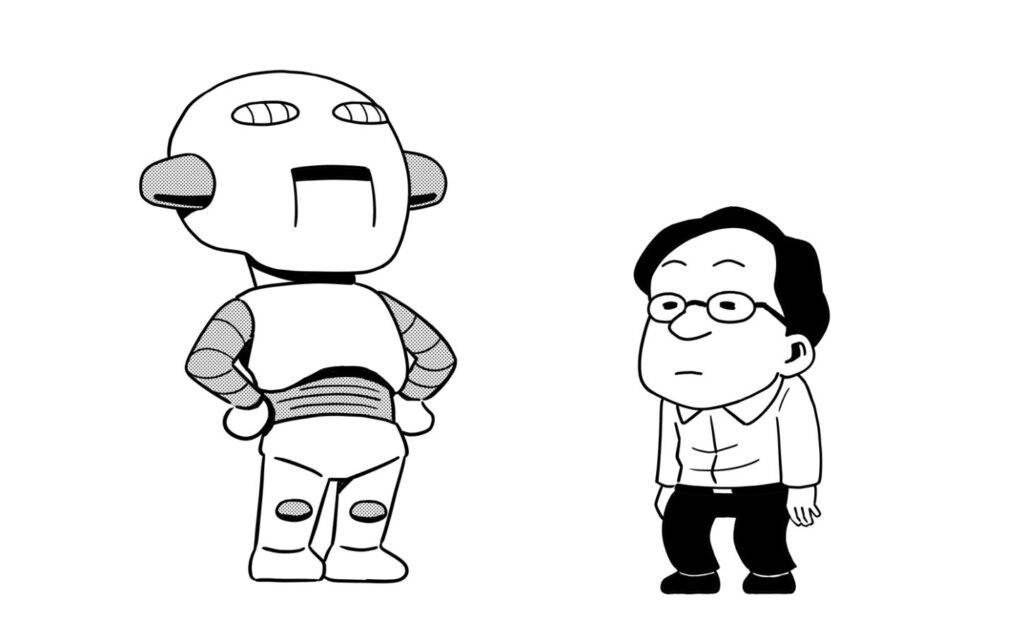
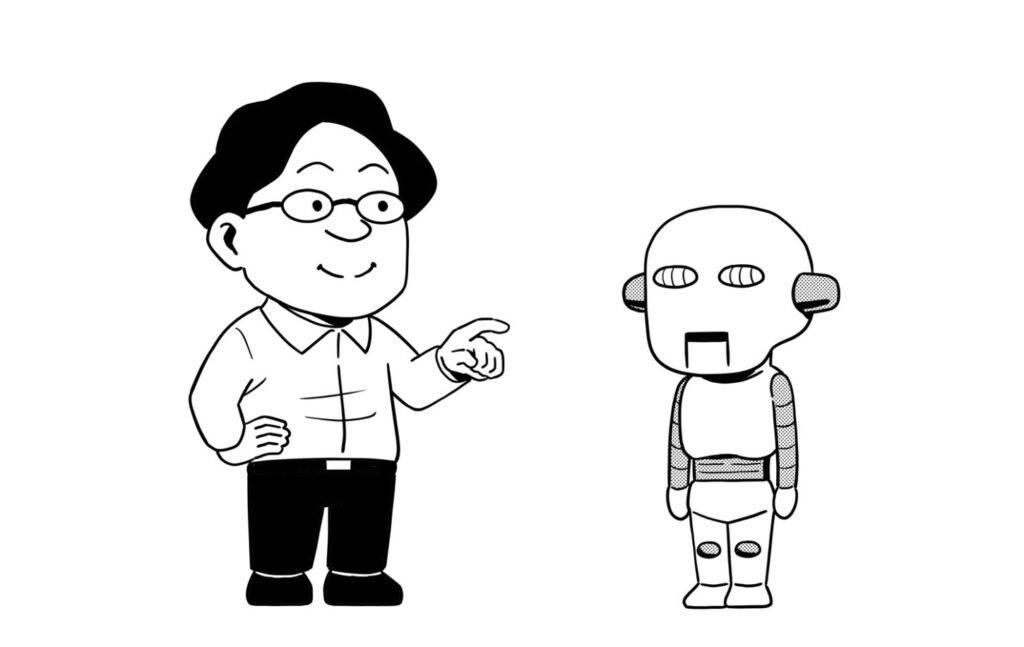
考えておいてください。
社会人大学
代表コンサルタント
桑名 伸
「学校で教えてくれない社会の授業」では、皆さまの取り上げて欲しいテーマや、ご意見、ご感想をお待ちしております。
>>学校で教えてくれない社会の授業ご意見、ご感想投稿フォーム<<


