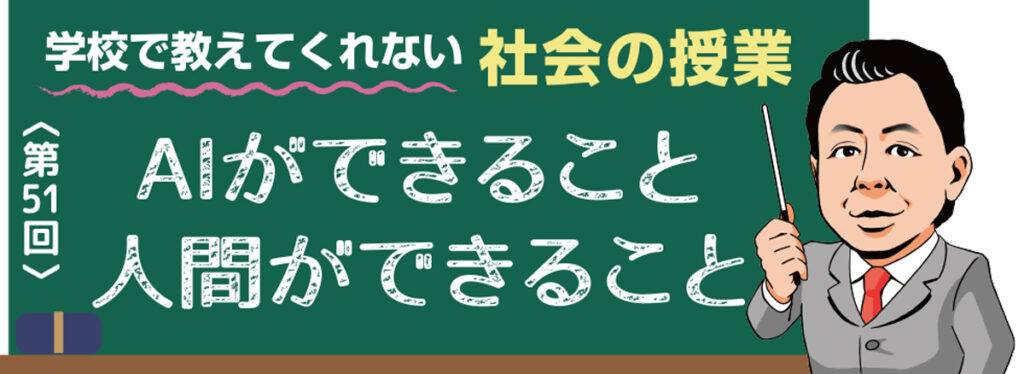
【2025年8月23日号 vol.51】
社会人大学 代表コンサルタントの桑名 伸です。
「学校で教えてくれない社会の授業」では、学校では教えてくれない社会の本質を学び、幸せになるための(不幸にならないための)正しい考え方についてお伝えします。
AIができること
人間ができること
最近は考えなくてもよい(?)ためのツール、AIが話題になっています。
「考えないことのリスク」「AIの間違った利用によるリスク」は皆さんの人生に非常に大きな悪影響を与えることなので、これについて、しばらくこの授業で深掘りをしていこうと思います。
以前、みやんぬさん(26歳・男性)から
会社で上級職の方が考えずチャットGPT(以下AI)で答えを出していて、今後の仕事はAIに置き換わるのではないかという危惧を持っている。自分で模索して導き出す過程が自身の血となり肉となり人を成長させ人生を豊かにさせると思う。
という意見をいただきました。(6月14日号)
AIについてお話しするにあたり、実際にAIがどのようなものなのかを実例をもってお知らせしようと思います。
読者から相談が来ています。AIを使ってみましょう。
今回はマイクロソフト社のCOPILOT(AI)を使ってみました。
(チャットGPTでも同様の結果が得られています)
質問内容に誤字とわかりにくい部分がありましたので(ゆゆさんごめんなさい!)AIに修正と要約をさせてみました。
投稿ネーム:ゆゆ 41歳 女性
仕事をしていて時々思うのですが上司や取引先に対して「忖度して」先回りして動くことは「甘やかし」に過ぎないのか?ということです。
某芸能グループの上層部がある記者会見で「日本社会は忖度がはびこっている」と言っていたのは印象的ですが「どの程度の忖度」であれば需要されやすく、どの程度の忖度であると甘やかしや馴れ合い、組織をスポイル可能性があるというのが私の疑問です。
古来から我々日本人は「察する」ことを美徳として、それが不得意なものは社会不適合者と見做される時代も長かったと思います。ここ20年くらいは多様性を受容する世の中になっては来ましたが、忖度に疲れ気味です(もちろん具体例はここでは書けませんが)
AIの回答★修正された文章(読みやすく整理)
仕事をしていると、上司や取引先に対して「忖度して先回りすること」は、果たして本当に良いことなのか、それとも単なる「甘やかし」なのかと疑問に思うことがあります。
以前、ある芸能グループの上層部が記者会見で「日本社会には忖度が蔓延している」と語っていたのが印象的でした。
私が考えたいのは、「どの程度の忖度」であれば相手にとって有益であり、どこからが甘やかしや馴れ合いになってしまい、結果的に組織をダメにしてしまうのかという点です。
日本人は昔から「察する」ことを美徳としてきましたし、それが苦手な人は社会不適合者と見なされるような時代も長く続きました。最近20年ほどで多様性を受け入れる社会に変わってきたとはいえ、私は今でも「忖度」に疲れていると感じることがあります。
◎AI要約(ポイントだけ抽出)
「忖度して動くことは、時に『甘やかし』や『馴れ合い』になるのではないかと疑問に感じている」
「日本社会では忖度が根深く、ある芸能人もその問題を指摘していた」「忖度の『適切な範囲』と『過剰な忖度』の境界が曖昧で、それが組織に悪影響を与える可能性がある」
「日本人は『察する文化』を重視してきたが、今は多様性の時代。とはいえ、忖度に疲れていると感じる」
桑名がAIへ返信★
ありがとう。先ほどの文章は私の記事の読者からの投稿です。どう答えてあげればよいですか?
AIの回答★
桑名さん、読者からの投稿があの文章だったのですね。それなら返信は共感・理解・思考の促進を軸にすると、誠実で心に響くものになります。
◎AI返信案:少しエッセイ風に寄り添う
「忖度に疲れた」という言葉が胸に刺さりました。私たちは長い間〝空気を読む〟ことを美徳としてきました。
でも、空気ばかり読んでいると、自分の呼吸が浅くなってしまうこともありますよね。忖度が信頼を生むこともあれば、責任の所在を曖昧にし、組織を弱くすることもある。その境界線は、まさに今、問い直されるべきなのかもしれません。
ご投稿のような声が、これからの働き方や人間関係のあり方に光を当ててくれると感じました。ありがとうございます。
AIを使っていない方は「こんなことまでできるのか!?」と驚かれたことでしょう。
これだから世間を騒がせているのです。仕事を奪われるというのも分かる感じがしますが、私が答えを出すと次のようになります。人間バージョンです。(笑)
◎人間の回答
ゆゆさんは気遣いの出来る方なのですね。そうでなければこの悩みは起きません。気遣いをすることは特に日本では重要なスキルです。素晴らしい能力ですから自分の行動を否定しないでください。でも疲れてしまうのが問題。一番良い状態は「忖度をしながら疲れない」こと。それができれば最高ですよね。
まず、なぜ疲れてしまうのか探りましょう。疲れる原因は「常に迷いながら」忖度をしているからだと思います。
「これは甘えにならないか?」など、考えていることの連続が疲れと悩みになっていると思います。ぜひ一度やってみてください。「忖度」と「甘え」のボーダーラインをゆゆさんが設定してしまうのです。やり方はお任せします。
常にそのルールに沿って対応をして「いちいち考えない」でみてほしいのです。もしそれで問題が起きればそのボーダーラインをずらして再設定する。頃合いの良いところが見つかればそれでOKです。ゆゆさんだったらできると思いますよ。
これが人間バージョンの答えです。内容の違いをどう感じましたか?
次回もこの続きを行います。
社会人大学
代表コンサルタント
桑名 伸
「学校で教えてくれない社会の授業」では、皆さまの取り上げて欲しいテーマや、ご意見、ご感想をお待ちしております。
>>学校で教えてくれない社会の授業ご意見、ご感想投稿フォーム<<


