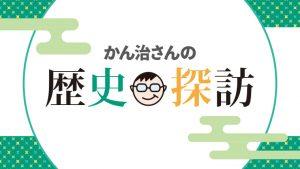東勝寺(湘南台)は得宗北条氏 ゆかりの寺という言い伝えが…
点燈山東勝寺は臨済宗円覚寺派の寺院です。元弘3年(1333)5月に鎌倉葛西ヶ谷の青龍山東勝寺で得宗北条高時一族は滅亡します。 この北条一族を悼み、秋雄(しゅうゆう)和尚(同寺開山)が南北朝時代(1300年代)に密かに建立 […]
本覚寺(小町)で見つけた 今年の干支・ウシの彫り物
本覚寺の境内の鐘楼には十二支がいて、今年の干支(えと)・ウシの彫り物を見つけました(写真・右下)。 ここの釣り鐘は、開山の日出上人が木更津八幡宮寺(上総の国)の僧との法論で勝利し八幡宮側は釣り鐘を差し出します。とても持ち […]
長後天満宮(藤沢市)の 主祭神、菅原道真公とは…
古くから天神とは天から降臨の地に恵みを与える神として各地に祀(まつ)られます。そして天神様といえば菅原道真公ですね。平安時代に天皇の御信任が厚く醍醐天皇の時に右大臣となりますが、左大臣のザンゲンで太宰府に流され当地で亡く […]
旗上弁財天社(雪ノ下)は 源氏池に鎮座
源頼朝は治承4年(1180)8月に旗上げをして、10月に鎌倉入りし鶴岡八幡宮を由比ヶ浜辺より遷宮、僧良暹(りょうせん)、大庭景義等に命じて源平池を造らせました。 源氏池には島を三つ造り、三は産で源氏繁栄を、平家池には島を […]
妙隆寺(小町)は鎌倉幕府有力 御家人屋敷跡に創建
妙隆寺は鎌倉の小町大路沿いにある日蓮宗の寺院です。この周辺一帯は源頼朝の有力御家人千葉氏の屋敷跡と言われ、その子孫が至徳2年(1385)、日英を開山に創建。開山日英の甥が第二祖日親です。 本堂の右手前の池は日親が寒中、百 […]
二伝寺(渡内)は 玉縄城の砦として創建
玉縄城(現在本丸跡は清泉女学院内にあります)は北条早雲が三浦氏攻略のために築城し、その砦(とりで)として永正2年(1505)に初代玉縄城主北条氏時が創建したのが二伝寺です。 玉縄城とは尾根続きで玉縄城砦の中で一番高い場所 […]
源義経ゆかりの満福寺(腰越) に伝わる「腰越状」とは
満福寺は義経ゆかりの寺としておなじみです。義経は平家を壇ノ浦でやぶり、凱旋して鎌倉入りを果たそうとしますが兄頼朝に足止めされます。この寺で有名な「腰越状」を書き、頼朝に和解を得ようと差し出しますが許されません。これは、義 […]
密蔵寺(藤沢)のご本尊・ 愛染明王は恋愛成就のご利益が
密蔵寺(藤沢市片瀬)は鎌倉時代の末に有弁僧正によって開かれた真言宗の古刹(こさつ)です。ご本尊は愛染明王で、愛を成就させてくれるご利益があります。 また、藍染(あいぞめ)の藍から染物業の守護神としても知られています。 密 […]
杉山和一は江島神社への参籠で 大出世をしました
杉山和一(わいち)は慶長15年(1610)伊勢の津に生まれ、5歳の頃に病が原因で不幸にも失明し、17歳で江戸に上り、鍼術(しんじゅつ)を学びます。和一は鍼術上達の願いで江島神社に参籠して、結願の日に下之宮(辺津宮)の石に […]
寺名は浄妙寺で地名が浄明寺 (鎌倉)なのは…
鎌倉市浄明寺は鎌倉五山第五位の浄妙寺に始まる地名ですが、江戸時代には、「浄妙寺」とも「浄明寺」「常明寺」とも書かれていたようです。 現在の地名「浄明寺」になったのは、諸説ありますが、格式の高い寺名をそのまま使うのをはばか […]